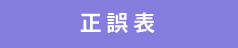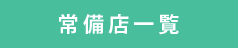オンライン書店で購入
更新: 2022年11月22日
関連書籍

金属錯体の機器分析 (上)
A5・上製・298頁/定価 4,620円(本体4,200円)

多核種の溶液および固体NMR
A5・上製・2色刷・384頁/定価 4,620円(本体4,200円)

金属錯体の電子移動と電気化学
A5・上製・2色刷・252頁/定価 3,960円(本体3,600円)

金属錯体の量子・計算化学
A5・上製・540頁/定価 8,140円(本体7,400円)

金属錯体の現代物性化学
A5・上製・420頁/定価 5,390円(本体4,900円)

フロンティア機能高分子金属錯体
A5判・上製・550頁/定価 8,800円(本体8,000円)

フロンティア生物無機化学
A5・上製・2色刷・548頁/定価 8,250円(本体7,500円)

錯体化学 ― 有機・無機複合体の分子科学 ―
A5判・上製・2色刷・496頁/定価 6,050円(本体5,500円)