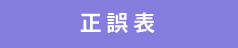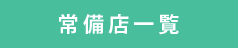オンライン書店で購入
更新: 2025年9月3日
関連書籍
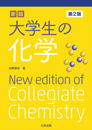
新版 大学生の化学(第2版)
B5・並製・2色刷・272頁/定価 2,970円(本体2,700円)

新版 大学の化学への招待
B5・並製・2色刷・246頁/定価 2,750円(本体2,500円)

新版 教養の現代化学(第2版)
B5・並製・2色刷・214頁/定価 2,640円(本体2,400円)

化学の世界への招待(第3版)
B5・並製・264頁/定価 2,970円(本体2,700円)

基礎化学 ― 化学と物質 ―
B5判・並製・2色刷・182ページ/定価 2,970円(本体2,700円)

基礎の化学
B5・並製・2色刷・154頁/定価 2,420円(本体2,200円)

化学の基礎 ~原子から生命現象まで~
B5判・並製本・2色刷・202ページ/定価 2,970円(本体2,700円)